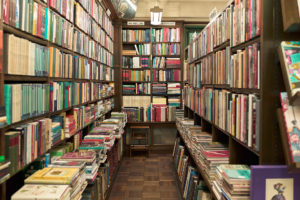思いやりも包む、ふくさ
貴重品を守る
結婚式などお祝いの気持ちを贈るご祝儀袋や、悲しい別れを悼む不祝儀袋。それを包む小さな布が「ふくさ」だ。ふくさは元々、貴重な品が収蔵された箱を、汚れや日焼けを防ぐ目的でかけられていた。現在でも「かけぶくさ」と呼ばれ、儀礼などで使用されている。そのときの「ふくさ」は「袱紗」と表記するのに対し、贈り物の金品を包むときや、茶道の茶道具を拭き清め、茶碗や器物を扱うときに使うふくさには「帛紗」の文字をあてる。

お祝いは左、お悔やみは右
ふくさは、衆議院の解散時にも目にすることがある。衆議院議長が解散を宣言する際、天皇陛下による解散詔書の写しは紫のふくさに包まれ、内閣総理大臣の伝達書とともに黒塗りの広盆に乗せられ議長に渡されるのだ。
一般的に使用されることが多いのは慶事・弔事だ。お祝いごとには、ピンクや藤色などの明るい色、不祝儀ごとはグレイなど落ち着いた色が用いられる。平安時代から高貴な色とされた「古代紫」は、礼を尽くした色として慶事・弔事の両方に使用される。たたみ方は、お祝いごとならご祝儀袋をふくさの上に左向きに置き、左側から折る。不祝儀ごとは右向きに置き右から。渡すときには、ふくさを開いてご祝儀袋・不祝儀袋を取り出す。相手にわざわざ見せないけれど、贈り物を大事に運ぶ気持ちがふくさに込められている。

大人になったら、ふくさを1枚
天保8年(1837年)創業の「銀座くのや」では、小さな風呂敷状の正式なふくさのほかにも、ポケット状に仕立ててある略式の金封ふくさが人気だという。模様入りのものがあったり、内側に自分の名前を入れたりと、バリエーションも豊かだ。大人になったら、まずは古代紫のふくさを1枚。それから、慶事用、弔事用をそれぞれ揃えてもいい。奈良時代にはすでに文書を包んだり、箱を守るために使われていたふくさ。日本に長く伝わる、ものを大切にする気持ち、相手を思いやる気持ちが込められたGOOD MANNERアイテムだ。

データ
| いつ始まったの? | 奈良時代には、掛け袱紗として使用されている。 |
| どこで見ることができるの? | 結婚式場や葬儀場。また衆議院解散時のTV中継など。 |
| 数字データ | ふくさは広げると正方形の形。一辺は約45〜50cm程度。 |
| 注意事項 | ふくさは絹製が多いため、水洗いは厳禁。 |
取材協力:
銀座くのや