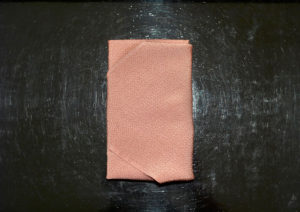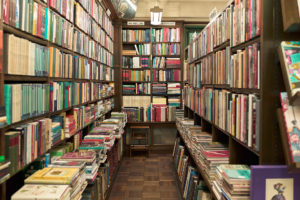社会人のための、和室の所作
和室の基本は上座と下座
日本の伝統的な生活様式である畳敷の和室。近年はフローリングの住居が増え、社会人になり改めて和室のマナーを学ぶ人も多いはず。そこで、京王プラザホテルの「テーブルマナー&お作法プラン」で講師を務める蒼樹庵 女将の土屋陽子さんに、社会人が知っておきたい和室マナーを聞いた。
「まず基本となるのは席次の把握から。人数や部屋の形状によっても異なりますが、主賓の上座は入り口から一番遠い床の間側のお席です。そして4人以上の場合は端ではなく中央になります。幹事や年下の方がお座りになる下座は入り口に近い場所を目安にしてください」。和室ではこの席次が基本となるが、部屋の形状によっても変わってくるので、マナー講座を受講したり、お店の人に尋ねたりするのがベスト。

動作の基本は上座向き
部屋に入るときは、上体を上座の方向に向け、襖や障子に対して斜めに座る。つま先を立てて正座をする「跪坐(きざ)」の姿勢でもよい。襖に近い方の手をかけて少し引き、そのまま手を下に滑らせ体の中央くらいまで広げたら、反対側の手に替えて自分の体が通るくらいまで開ける。入室するには、座ったままで躙(にじ)りながら移動する「膝行(しっこう)」で。段差がある場合は下座側の足から入る。そして、畳の縁はなるべく踏まないこと。これは、かつて格式の高い武家や商家が畳縁に家紋を入れる風習があったことからきている。家紋を踏むことはご先祖様の顔を踏むのと同じとされたことから生まれた。
流れるような美しい所作は、その人の印象を格段にアップしてくれる。



お辞儀は「真・行・草」
部屋に入ったら、ご挨拶をお忘れなく。お辞儀には「真(しん)・行(ぎょう)・草(そう)」と3パターンあり、ビジネスシーンでは「行」のお辞儀を意識しよう。「草」が軽い会釈であるのに対し、「行」は目上の方に対して45度の角度まで上体を傾ける。深く上体を折り曲げる最敬礼の「真」は、神仏に参詣するとき。また、座布団に座るのは招待者側に勧められてから。注意したいのは、座布団は決して足の裏で踏まないこと。他にも気をつけたい和室のマナーは、身だしなみ。夏場のサンダルスタイルのまま、素足で和室に入るのは失礼にあたるので、女性は事前に化粧室でストッキングを履くなどして身だしなみを整えよう。男性は、スーツのジャケットを脱ぐのは主賓や会の幹事に勧められてから。全てのマナーの根底になるのは、目上の人を敬う気持ち。さらにマナーの背景を学ぶと、日本の文化を知ることにもなるTOKYO GOODなのだ。

データ
| いつ始まったの? | 和室作法は、茶道や武道に源流があると言われているが発祥は諸説ある。 |
| どこで見ることができるの? | 正しい作法を学ぶなら、京王プラザホテルの「テーブルマナー&お作法プラン」へ。西洋料理や懐石料理の正しいマナーのほか、立食パーティのマナーなど3つのコースから選べる。 |
| 数字データ | 1.5488平米:「江戸間」と呼ばれる畳のサイズ。京間は1.82405平米なので、江戸は京都より畳の縁に注意が必要だったかもしれない。 |
| 注意事項 | 冠婚葬祭の場面でも役に立つ「跪坐(きざ)」と「膝行(しっこう)」の所作。独特な動きなので、社会人になったら練習しておこう。 |
取材協力:京王プラザホテル懐石 蒼樹庵